古今伝授の間
施設
古今伝授の間
説明
「古今伝授」とは、当時は最高の学問とされた「古今和歌集」の読み方や解釈を秘伝とし、それを師から弟子へと一子相伝したことを意味します。
この茅葺き屋根の歴史ある建物は熊本県指定重要文化財となっていますが、元々この地は「酔月亭」とされる御茶屋があったとされます。1877(明治10)年の西南戦争で消失し園内も荒廃した後、旧藩士らに払い下げ(官有地の売却)られた水前寺成趣園に1912(大正元)年に移築されたのが、この「古今伝授の間」です。
この茅葺き屋根の歴史ある建物は熊本県指定重要文化財となっていますが、元々この地は「酔月亭」とされる御茶屋があったとされます。1877(明治10)年の西南戦争で消失し園内も荒廃した後、旧藩士らに払い下げ(官有地の売却)られた水前寺成趣園に1912(大正元)年に移築されたのが、この「古今伝授の間」です。
歴史
この建物は元々は京都御苑の八条宮家(のちの桂宮家)の本邸内に建てられ、幼少の八条宮智仁親王が御学問所として使用されたと伝えられています。この場所は、京都御苑の北端中央付近、現在の今出川通に面する付近に位置します。
その後、京都御苑から長岡京へと移り、1871(明治4)年に細川家に下賜された後、1912(大正元)年に細川家と縁深いこの地へと復元されて今に至ります。
閉鎖されていた時期もありますが、お菓子の香梅により1998(平成10)年4月から再公開され、その後大幅な修復工事が実施され2010(平成22)年10月11日から一般公開されています。
その後、京都御苑から長岡京へと移り、1871(明治4)年に細川家に下賜された後、1912(大正元)年に細川家と縁深いこの地へと復元されて今に至ります。
閉鎖されていた時期もありますが、お菓子の香梅により1998(平成10)年4月から再公開され、その後大幅な修復工事が実施され2010(平成22)年10月11日から一般公開されています。
R7/3/12
古今伝授の間 香梅
 熊本県 ☕喫茶店
熊本県 ☕喫茶店
クリップボードにコピーしました



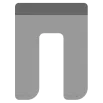 Taittsuu
Taittsuu